二人でHang in there
今回のテーマはHang in thereである。辞書を引いてみたところ、ピンチや危機にある人を励ますための言葉で、「負けるな」「頑張れ」という意味とのこと。耐えねばならない状況にある人にかけるイメージか。
大きなものから小さなものまで、ピンチは意外とある。たとえば、自分一人で何とかなるピンチ、一人ではどうにもできないように見えるピンチ。我々対人援助職は圧倒的に、後者の現場に立ち会うことが多い。というか対人援助職は、心理も含めてそのための専門職である。そしてたいてい、その解決や局面の変化には結構な時間と忍耐が必要だ。耐え忍ぶまもなく魔法のようにパッと何とかなるものはない。
かように、相談者が瀕しているピンチを時間と忍耐とスキルでもって分け持つ心理職とはどんな人々か?ピンチの乗り越え方を指南する人ではなくて、人が危機にある時共にいて、その危機を乗り越えた後、振り返って胸を撫で下ろすと同時にそこに居合わせられたことを光栄と思うことができる人たち、つまり、共にある人なんだとわたしは思っている。コーチでもないし、伴走者とも少し違う。すなわち、型通りの振る舞いを教えるのでもなく、共倒れの危機を孕んでもいけない。
シンプルに、危機にある人と共にあり続ける人が、心理職であると思うのだが、どうだろうか。
みこと心理臨床処を始める時だったと思うが、来る人のマイカウンセラーになりたいよね、と話したことを覚えている。初めてくる人はもちろんだが一度相談が終結したり途切れたりしても、その人が困った時、一人でHang in Thereしなくてはならなくなった時、私たちのことを思い出して相談してみようかと思ってもらえるカウンセラーのいるところとしてみことを使ってもらえたら嬉しいよね、と。
開業時には、長らく組織の中で働いてきた自分が開業してどんなことが出来るか分からなかったが、考えてみたらクライエントと2人でHang in Thereする根性は人一倍だし、これまで心理職として得てきた経験、会得した専門性・スキルと合わせて、のびしろまである。どんとこいである(ホントか?ホントだ)。
ところでHang in Thereと言えば私のなかではCHAGE&ASKAのYAH-YAH-YAHなのだが、私のなかではイントロだけでもテンション爆上がりするうたナンバーワンである。徹頭徹尾、どこを切り取ってもテンションが上がるようにできていると勝手に思っているが、Hang in Thereについて考えてくると、最後のコーラスで語り掛けられているのは困難な状況にある人だったのか、とここではたと思い当たる。
「Hang in There 病まない心で/Hang in There 消えない心で」
というからにはもしかしたら病みそうで消えそうな心を抱えた人、ということか。そう思って聴くとうたの解釈までまるで変わる。傷つけられた人に「牙を剥け」「今から一緒に殴りに行こうか」という畳みかけ。すごい。励ますというよりアジテートするうたじゃないか。そりゃテンション上がりますね。
(C.N)
コラム(テキスト版)倉庫
お問い合わせはコチラまで
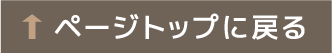

![]() ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。