不自由の中の自由
『自由在不自由中(自由は不自由の中にあり)』
by福沢諭吉
「自由」って何だろう?
と、教育臨床に携わっている身としても、よく考える事柄である。
そんな時に、思い起こされるのが、上記の福沢諭吉の文章だ。
この文には、
自由について、「ひと口に自由といえば我儘のように聞
こゆれども、決して然らず。自由とは、他人の妨をなさ
ずして我が心のまに事を行うの義なり。」と前置がある。
この前置き、少し難しいのでAIに現代語訳を頼ってみよう。
『「自由」と一口に言っても、わがままのように聞こえるかもしれないが、決してそうではない。自由とは、他人の邪魔をせずに、自分の思うように行動することである。』
他人の邪魔はしない。でも、自分の思うように行動する。
これは、非常に難しくはあるまいか。
しかし、他人の邪魔をしないという不自由さの中にしか、
人と人とが関わるこの世界には、自由は存在しない。
もし、他人の邪魔をしないことを不自由だと感じるなら、こう考えてみればわかりやすい。その「他人」が自分だったら?
誰もが他人に邪魔されず、自由に過ごしたいと願うはずだ。ならば、自分も他人の邪魔をしない。その上で、自分の思うように行動できるよう、お互いに模索していく必要がある。そうでなければ、「自由」な世界や自由な生き方は実現できない。
自由というのは、「無秩序」とは違い、なんて高度で文化的な活動なのだろうか。
では、個々人が「自由」を自分で考えて実践するにはどうすればいいのか?
まず、他人の邪魔にならない行動とは何かを見極める必要がある。これは人によって異なるため、相手の気持ちや思考を理解し、何が邪魔になるのかを読み取ることが求められる。これは簡単ではない。
さらに、「自分の思うように行動する」ことも、簡単そうで実は難しい。自分が本当は何を望んでいるのか? 自分のことは自分が一番よく知っていると思いがちだが、意外とそれがそうでもない。
日常の雑事や「しなければならないこと」に追われていると、やるべきことは頭に浮かんでも、自分が本当に「したいこと」がすぐには思い浮かばないことがある。
また、したいことが明確でも、思うように行動できない場合もある。例えば、美味しい料理を作りたいと思っても、思うような結果にならなければ、「自分の思うように行動した」とは言えないかもしれない。
他人を知ること、自分を知ること、そして望む行動をすること。これらはすべて、意外と難しいのである。
そこで、私たち人間の社会には「ルール」が生まれたのかもしれないと思う。
ルールとして明文化すれば、何をすればいいかが明確になり、とりあえず「他人の邪魔をしない」状態を作りやすい。少し不自由かもしれないが、その中で好きなことができる。
また、自分と他人の間に境界線を引くことも大切だ。相手の考えがすべてではなく、自分の考えと分けていく作業。人がこう思うとしても、自分はこう思う——そんな自立した思考が重要だ。
そして、もう一つ大事なことがある。思うように行動したくてもできないとき、スキルを磨くことも必要だが、苦手な部分を手伝ってくれる人や、補ってくれる仲間がいるというのはとても大事だ。
一人ですべてを思うままにできるのは、超人だけではないだろうか。
自分の苦手を誰かが補い、誰かの苦手を自分が補う。そんな助け合いの中で、回っていく日常。
そのためには、話し合い、ルール、ちょっとした我慢、相互理解、そして「お互い様」の精神などが必要だ。
多くの要素を詰め込んで、不自由の中の自由を私たちは模索する。そして、それを楽しんでいけたら、良いのにと思う。
(K.N)
コラム(テキスト版)倉庫
お問い合わせはコチラまで
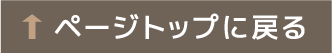

![]() ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。