察すること
察するとは、「察知すること。(人の心中や物事の事情を)おしはかる。推測する。また、は、おもいやること。」だという。
察しが良い人というのは、確かにいる。相手の雰囲気、しぐさ、表情などノンバーバルな部分を見て非常に細やかに判断する。しかし、一般的には親しい人に対する方が、察することの感度が良い場合が多い。なぜなら、いつもその人を傍で見ているため、何を考え、何を欲するかを推測しやすいからだ。それは、パターン学習と言っても良い。
よくあるのが、常連のお客さんが買い物や食事に来た時、「いつものですね」と頼まれる前から、店員さんが確認してきたりする、あれである。
察してもらった側からすると、「いつもの」ものが、敢えて言わなくても出てくるという楽さだけではなく、自分のことを分かってくれているという安心感や嬉しさ、受け入れてもらっている気持ちに繋がったりする。
一方で、今日はたまには、「違うもの」を頼みたかったのに、言い出せなかった…と、逆に気を遣ってしまう場合もある。
でも、それはお客の方が、声に出して言わなければ伝わらない。察することに長けている店員さんなら、そのお客さんの「違うものの方が…」と思う一瞬の間を感じ取って「あ、でも今日はたまには別のにします?」と聞いてくれるかもしれないが…。
日本は察する文化と言われ、それは美徳とされる。
しかし、いつまで美徳でありつづけられるのだろうか?
というのも、最近はインターネットも発達し、とにかく色々なものが多様化してきた。つまり、昔ならば、察するために必要な情報がそこまで多くなかったというか、社会的な背景とか、「これってこういうもの」という暗黙の了解が、日本人の中でもちやすい同質性の高い社会だった。
しかし、今や文化は多様化し、社会的な背景が異なる人たちが増えてきた。
SNSでは個々の意見が可視化され、かつての「暗黙の了解」が共有しづらくなっている。例えば、Z世代と団塊世代では価値観が大きく異なり、同じ日本人同士でも背景が違い、考え方も違う。都市と地方、職業やライフスタイルの違いもある。そう考えると、察することが、しにくくなっているし、美徳でもなくなってきていると思える。
このような多様化のなか、「声に出さないと伝わらない」場面も増えている。察することに長けた店員が客の微妙な変化を感じ取ることもあるが、それはあくまで例外だ。グローバルなビジネス環境や、直接的な表現を好む若者文化の影響で、明確なコミュニケーションが求められる場面が増えている。
察する文化が薄れ、個々の意見を尊重する社会へと移行するなか、「空気読めない」という揶揄は、そのうち、揶揄ではなく、死語になるのかもしれない。
空気は読めないのが当たり前の社会になれば、あまり空気が読めないから、自分はコミュニケーションをとるのがうまくないのだと、卑下することは無いかもしれない。
空気を読むことよりも大切なのは、相手に対する関心と理解したいと思う気持ちではないだろうか。そのためには、相手の言葉に耳を傾け、質問を通じて理解しようとする姿勢や、話し合いで互いの意図を確認する努力をつづけていくこと。それが一番の美徳になっていくと、優しい文化が新たに生まれるのかもしれない。
(K.N)
コラム(テキスト版)倉庫
お問い合わせはコチラまで
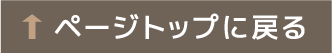

![]() ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。