卒業の行方
教育の現場で長く臨床の仕事をしていると、どうしても「卒業」というものに良くも悪くも敏感にならざるを得ません。
なぜなら、心理士としての仕事を始めて20年ほど、ほぼ毎年のように多くの子どもたちとその保護者の方を見送ってきているからです。そして、教育相談やスクールカウンセラーという仕事は、子どもたちの卒業と同時にほとんどの場合が終わりになります。
それこそ、仕事を始めたばかりの時は、私自身は卒業式や卒業にそれほど思い入れを持っていませんでした。なので、子どもたちが望むならそのような形で、卒業できればそれで良いと単純に思っていたものです。3年生全体で行ういつも通りの卒業式に出席するのでも、卒業証書を放課後に学校に取りに行く形でも、保護者の方だけが受け取ることでも、そんなに大きな変わりはないだろうと。
しかし、とある適応指導教室(不登校の子どもたちが通う公立のフリースクール。教育支援センターともいう)で行われた卒業を祝う会に出席したのをきっかけに、私の認識は大きく変わりました。
適応指導教室は子どもが所属する学校という位置づけでは無いので、卒業式というものは行われないのですが、教室ごとに色々な形で子どもたちの卒業を祝います。その中で、一人一人の子たちに渡された卒業を祝う証書のようなもの。その中に、子どもたちを見守ってきた先生や職員の方たちの想いを垣間見つつ、それを受け取る子どもたちの緊張した面持ちや、嬉しそうな顔。そして、その会をやり遂げたという気持ち。色々なものが伝わってくる良い会でした。
この会をきっかけに、子どもたちが、たとえ少し緊張するとしても、自分たちの納得する形でやり遂げ、卒業を迎えるということの大切さを実感したのです。
その後も色々な形の卒業式に出会ってきました。いつもは学校に行けてない子が、卒業式だけは出たいと言って参加する姿や、渋々ながら卒業証書を放課後に取りに行ったら思いがけず先生方に祝ってもらえて困惑したりでも少しうれしそうだったりする姿や、学校には絶対に行かないと決めた子が、卒業証書を家まで届けに先生が来たから自分で受け取ったと話す姿などなど。
色々な形があっても、一つだけ共通していることがあるのではないかと私は思っています。
それは、子どもたち自らが卒業をどういう形で迎えるか、ただただ考えるのが嫌だというだけの気持ちではなく、大人からどうするか問いかけられ、悩み、勇気を出し、自分の気持ちを大切にした上で出した結論だということです。
そう、それが自分の気持ちを一生懸命考えて出す、自分なりの主張であり、自立の一歩であり、今いる場所から飛び立つためのイニシエーションなのだと思います。
だからこそ、普段は子どもたちに寄り添うように話しを聞いていたとしても、卒業の時には、嫌な顔をされても私は問いかけます。今まで一緒に悩んだり、時には笑ったりして共に過ごしてきた中の集大成として、最後の課題に一緒に取り組むために。
「卒業式は、どうする?」
と。
(K.N)
コラム(テキスト版)倉庫
お問い合わせはコチラまで
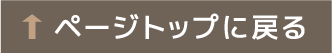

![]() ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。